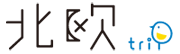深夜に突如姿を現す衝動。
あの人のように絵筆を取って、白いキャンバスを色で埋め尽くしたいと思った。
たまに何のバックグラウンドもないものに、不朽の憧れを抱くときがある。
それは一種のコンプレックスや劣等感に限りなく近い。
私はそれを、言葉で埋め尽くすことしかできない。
でも私には感情がひとつ、大きく剥落してしまったペンしか手元に残っていない。
まるで当時の栄華を語ることすら困難な、修復の必要なフレスコ画のような。
数年前愛した人がいた。
彼は私の書く文章が好きだと言った。
感情的に私を叱咤しながらも、その言葉を繰り返した。
彼のシンプルすぎる言葉が、逆に打ち寄せる波のように胸に響いたことを今でも覚えている。
彼だけではない。
それ以来同じ褒め言葉を使う男性には、思わずはっとしてしまう。
必要以上の比喩と修飾語で飾り立てた言葉たち。
その中には、本当はひとつの感情しか織り込まれていない。
あの人はきっと、それを見抜いていたのかもしれない。
再び静かに歩き出そう。あのときどこかへ行ってしまった感情の欠片を探しに。